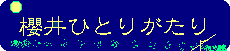「まごころ」
ふもとの名刹に参ったあと、長い坂道をのぼった。首筋の汗をぬぐうついでに谷あいの町を振り返ると、家々の瓦が銀箔のように真昼の陽を映していた。
高台に建つ私鉄の駅についた。ふだんは鈍行しか停まらない無人駅だが、この五月連休と盆正月の間だけ急行が臨時停車する。そのため駅舎の入口には券売の職員が控え、煤けた待合室にはリュックを背負った年配客の姿が目だっていた。
踏切を渡って下り方向のホームを歩く私を、がぼっ、がぼっという靴音が追いかけてきた。ベンチに座る前に足音の主をたしかめた。ビニールの前掛をつけ、ゴム長靴を履いたおばあさんと、そのうしろでスチール台車を押す若い娘さんが目に入った。
私より、ひとつ駅舎寄りのベンチに二人は腰を降ろした。まずおばあさんが「あんたはよくやるねえ」と少女に話しかけた。相手は線路の向こうの藪を眺めたまま、「はあ」と気のない返事をした。
「今年でいくつになった」
「十七です」
「そうか、遊びたい年頃なのに、あんたはほんとうによくやる」
「べつに、休みの日は人並に遊んでるし」と、少女は憮然とした口調で答えた。おばあさんは、相手の反応など意に介さぬ顔つきで「あんたはよくやる」の文句を繰りかえした。
下りの鈍行が駅に近づいてきた。台車とともに二人は一両目の乗車位置に移動した。
ドアが開くと、少女はすばやく客車に乗り込んだ。そして乗降口の際に積まれていた荷を、外で待つ相棒に手渡した。次々と台車に積まれてゆく発泡スチロール製の箱には、隣町の漁協名を印刷したシールが貼られていた。
荷は、二列積みで五段くらいの高さになった。下段の箱に亀裂が入っていたらしく、赤い滴が荷台をつたっては舗石にしたたり落ちていた。車掌が目ざとくそれを見つけ、「おまえら、また汚しやがって」と少女をにらみつけた。
出発の笛が鳴った。少女は肩で息をしながら、動き出した列車を見送っていた。そのかたわらで積荷の角をそろえていたおばあさんが、「あんたはよくやるなあ」とつぶやいた。
少女が振り返った。若者らしい、貧血の様相をともなう怒りが、暗い眉間の皺にあらわれていた。手元に目を落としたままのおばあさんは、青く顔色を変えた相棒に気づかず、「遊びたい年頃なのに……」という文句を言い添えた。
いきなり「うるさい」という叫びをあげ、少女が台車上の荷物を蹴飛ばした。スチロールの山が崩れ、フタが外れた箱の中から、生の魚や氷の粒があふれだした。なおも「だまってろ、くそばばあ」と吐き捨てて、少女は足早にホームを立ち去った。
おばあさんは散らばった荷を集め、台車にきちんと箱を積みなおした。そのあと不意に頭をめぐらせ、柱越しに向き合う私に目を留めた。
とっさのことで、私には狼狽の色を隠す隙もなかった。すべて見られていたと悟ったのだろう、それは誤解だと言わんばかりの口ぶりで、彼女は訴えかけてきた。「箱がくずれたのはワシのせいだ。あの子は、ほんとうによくやるんよ」
まともに相対するビニールの前掛けは、赤く濁った汁に汚れきっていた。鼻をつく生臭さに私は顔をしかめた。すると、おばあさんはあきらめたように首を振り、のろのろと台車を押しはじめた。
鳴りだした鐘の音にせかされ、彼女は踏切を渡り終えた。山裾の緑を分けて急行の黄色い車両が近づいてくる。私は鞄を肩にかけて立ち上がった。直後、敷石の窪みを流れて足元に迫る水に気づき、白いズック靴の汚れ具合をたしかめた。
了
|